一般財団法人河田病院 インタビュー
日時:2025年2月5日 14:00~16:00
インタビュイー:河田敏明院長
精神保健福祉士 丸石幸嗣課長 中村佳代子副主任 相賀美幸
インタビュアー:管理者 大東真弓
顧 問 星昌子
取締役 八杉遼太
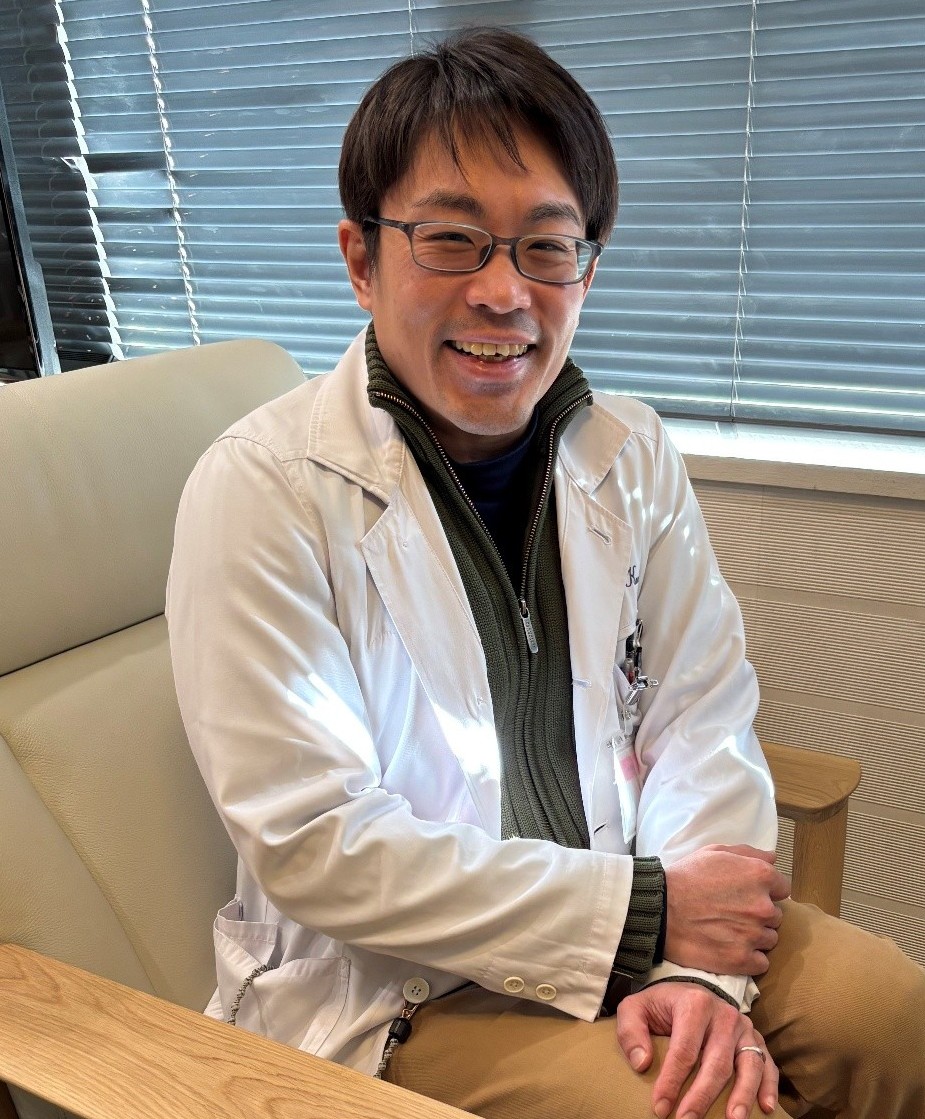
河田敏明 院長
訪問看護に期待することについて
河田院長
クライエントによって期待する内容は異なります。例えば、自宅退院が難しく、施設でも人間関係などの理由から適応できずに入退院を繰り返す方がおられます。入院期間が長くなると病院生活に慣れてしまい、施設への退院を拒否されるケースもあります。
施設へ退院された方への訪問では、1日でも長く施設で生活を続けられるよう、適切な声かけや生活場面の把握を行い、その方に合った支援を検討していただきたいと思っています。施設生活に馴染めるようなサポートを期待しています。
タウンサークル
グループホームによっては、世話人の方が積極的に関わってくださる一方で、「訪問看護は何をしてくれるのだろう」という疑問が生じることがあります。私たちは役割分担を明確にし、専門性を生かしながら、訪問看護でできることを見極めて実践することを心がけています。
グループホーム運営と地域支援について
河田院長
当法人もグループホームを運営していますが、「経営的に非常に厳しく、症状が活発でも入院せず生活を続けてもらわないと運営が成り立たない」という声を聞くことがあります。そのため、「入退院を繰り返す人は受け入れにくい」と考える気持ちも理解できます。特にグループホーム単体で運営している法人は本当に厳しい状況です。今年度は、昔からの職員寮を改修してグループホームを増設し、入退院を繰り返し支援が難しい方にも利用していただける環境づくりを進めています。
グループホームは独立採算としていますが、
「入院が必要なときは無理をせず入院してもらったらいいよ。」
というスタンスで運営しています。入院時は病院、退院後はグループホームで支援し、その方に合った環境を提供できれば良いと考えています。
また、認知症で改善が難しい症状があっても、「病院がバックにあるから安心」とご家族や本人が退院を受け入れやすくなるような体制を目指しています。
現在、グループホーム「一二三(ひふみ)」は7名、「ぽかぽか寮」は14名で、計21名の運営です。さらに定員5名のグループホームの開設を予定しています。
今後の重点領域について
タウンサークル
病院の正面に「認知症といえば」という看板がありますが、特に認知症支援に力を入れていくということでしょうか。
河田院長
認知症に限らず、発達障害や知的障害など、地域での生活支援が難しい方々への支援に力を入れていきたいと考えています。
訪問看護ステーションの現状と範囲
河田院長
現在、訪問看護ステーションには6名の看護師が在籍していますが、募集をしても応募が少ないのが現状です。訪問看護を拡大したいものの、簡単ではありません。
タウンサークル
多くの事業所では距離で住み分けされることがありますが、貴ステーションに訪問範囲の規定はありますか?
河田院長
厳密な規定はありませんが、シフト作成の段階で自然と訪問可能な範囲が決まってきます。倉敷や中庄は難しく、花尻あたりが訪問可能なギリギリの範囲だと思います。
タウンサークル
当ステーションは西・東・中央エリアなど複数拠点で訪問しているため、必要に応じてご活用いただけると嬉しいです。
人材と働き方について
河田院長
訪問看護の所長は「65歳までは働きたい」と話してくれており、力になっています。看護師はスキルを持っているため、実年齢にかかわらず若々しい方が多く、退職後も延長雇用制度を活用して働いてほしいと思っています。
タウンサークル
院内看護師の異動によって訪問看護が運営されているのでしょうか。
河田院長
私は、将来職責を担う看護師には病棟だけでなく訪問看護や地域連携室など、地域での支援を経験してほしいと考えています。とはいえ、なかなか実現は難しいのが現状です。
河田病院としての今後の展望
河田院長
当法人は病院・グループホーム・高齢者施設など多角的に運営しています。それぞれの強みを生かしながら、安定している方を受け入れるグループホームだけでなく、病状が不安定で入退院が頻回な方も受け入れられる体制を整えていきたいと考えています。
また、定員5名のグループホーム開設も、こうしたニーズ増を見据えた取り組みです。
病院がバックにある強みを生かし、医療と福祉を適切に組み合わせながら、安心して生活できる地域づくりに貢献していきたいと思っています。
精神保健福祉士の方々へのインタビュー

左:相賀美幸さん 中央:丸石幸嗣さん 右:中村佳代子さん
タウンサークル
タウンサークルを利用されていかがでしょうか?
河田病院MHSW
利用者の数はあまり多くはありませんが、利用した方々は丁寧な支援内容で満足されているように感じます。連携も問題なく出来ていたと思います。当病院は同じ法人に富町訪問看護ステーションがありますので、まずそちらに依頼をすることが多いです。
しかし富町は、24時間体制を取っていないことや距離の問題、性別などで他のステーションにお願いしなければいけない事が生じてきます。
タウンサークルの強みをお聞かせください。
タウンサークル
タウンサークルは12年前、岡山県精神科医療センターで精神科医療経験を積んだスタッフによって立ち上げられました。入院により症状は改善しているものの、自宅が遠方であるなどの理由で退院が難しい方に対して、「どこに住んでいても必要な地域支援を受けられ、安心して暮らしていけるようにしたい」という思いから事業を開始しました。
現在は、看護師 21名、作業療法士 11名、精神保健福祉士 2名、臨床心理士 1名が所属し、多職種によるチーム医療を強みとしています。特に24時間つながる安心感や、利用者との信頼関係の構築を大切にしています。
また、近年ニーズの高い発達障害や児童支援の訪問看護にも力を入れています。
対応エリアは、岡山市内はもちろん、倉敷市・井笠・高梁市・吉備中央町・備前市・御津町・赤磐市など遠方にも訪問しています。
タウンサークル
長期入院の地域移行について、現場ではどのような困難があるのでしょうか。
河田病院 MHSW
地域移行の難しさは多岐にわたります。
何十年も入院していると家族との関係が希薄で帰る家や身寄りがないケースが多いです。長い入院生活により社会常識や他者との円滑なコミュニケーションがうまくできない場合があり、社会の変化に対応できずハラスメント行為などが見られるケースもあります。
強度行動障害がある方など発達障害支援センターなどと連携して退院支援を行なっても、退院後の受け入れ先となる施設の確保が大きな課題となります。
在宅で重度の障害を持つ人を支えるには、高度に専門的な支援体制が不可欠であり、特に家族の協力がない場合は困難が増します。
基本的には状態像にあまり変化はなく地域での生活に困難な状態にある患者さんが多いです。
強度行動障害のある方や長期入院で社会性を失った患者さんは退院先の確保が難しいです。そのような患者さんを受け入れる施設や支援体制が不足しています。
訪問看護だけに頼ることは難しいですが、やはり24時間365日いつでも必要時の利用が可能な在宅支援があれば退院することのハードルも下がっていくのではないかと思います。
色々なサービスや機関と連携していかなければ支えることが困難なケースばかりです。
お互いにそれぞれの組織のストレングスを利用しながらクライエントを中心に連携を強化できたらと思います。
一般財団法人河田病院 → 河田病院|岡山の精神科医療専門病院 歴史ある精神科専門病院として岡山の精神科医療に貢献いたします
